私たちは日常的に「覚える」と「憶える」という言葉を使いますが、これらの違いを意識することは少ないかもしれません。
しかし、これらの言葉には明確な使い分けがあり、それを理解することで、より適切に表現できるようになります。
本記事では、「覚える」と「憶える」の意味や使い分けの違いを詳しく解説し、実際の使用例を交えながら、その使い方を明確にしていきます。
覚えると憶えるの違い
覚えると憶えるの意味を解説
「覚える」と「憶える」はどちらも「おぼえる」と読みますが、意味や使い方には明確な違いがあります。
「覚える」は知識や技術を身につける意味が強く、特に学習や訓練によって習得する内容に対して使われます。
例えば、新しい単語や計算方法を習得するときに「覚える」を使います。
一方、「憶える」は感情や経験を心に留める意味が強く、単なる情報の記憶ではなく、特定の出来事や感情が深く印象に残る場合に用いられます。
たとえば、大切な人との思い出や、強く心を動かされた出来事を記憶するときに「憶える」を使います。
このように、「覚える」は意識的に学ぶ行為に関連し、「憶える」は無意識のうちに心に刻まれるものに使われることが多いのです。
そのため、使用するシーンや文脈によって、適切な漢字を選ぶことが重要になります。
覚えると憶えるの漢字の使い分け
- 「覚える」:勉強やスキルの習得、暗記に使われる。
- 「憶える」:経験や感情、思い出などを心に刻む際に使われる。
覚えると憶えるの英語表現の違い
- 「覚える」:”memorize”, “learn”, “remember”
- 「憶える」:”remember”, “recollect”
覚えると憶えるの実際の使い方

日常生活での使用例
- 「電話番号を覚える」
- 「昔の出来事を憶える」
文学作品における使い方
- 「あの日の彼の言葉を今でも憶えている。」
- 「この詩の一節を覚えておいてください。」
ビジネスシーンでの覚えると憶える
- 「新しいプレゼンの資料を覚える。」
- 「顧客との会話内容を憶えておく。」
名前を覚えると憶えるの使い方

名前を覚える場合の注意点
名前を「覚える」とは、単に記憶することを指しますが、「憶える」と使う場合はその人との関係や印象も含めて心に残すことを意味します。
つまり、「覚える」はデータとして名前を記憶することに重点を置いているのに対し、「憶える」はその名前に関連する感情や出来事を含めて記憶することが重要となります。
例えば、ビジネスの場面では取引先の名前を「覚える」ことが求められますが、顧客対応などでは、その人の好みや過去のやり取りを「憶える」ことで、より親身な対応ができるようになります。
感情を憶えるとはどういうことか
「憶える」は感情的な要素を伴うことが多く、例えば「恐怖を憶える」「感謝を憶える」など、心に強く刻まれる感覚があります。
これは、単なる情報の記憶ではなく、過去の経験や体験を通じて心に残るものです。
たとえば、幼少期に経験した楽しい出来事や辛い出来事は、単なる出来事の記憶ではなく、そのときの感情とともに深く心に刻まれます。
このように、「憶える」は単なる記憶を超えた、より強い印象や情緒的な要素を含んでいるのです。
具体例で学ぶ覚えると憶える
- 「先生の顔を覚える。」(顔と名前を一致させる)
- 「先生の優しさを憶える。」(その人の性格や行動が印象に残る)
記憶に関する疑問

記憶の定義と覚える・憶えるの関係
記憶には短期記憶と長期記憶があります。
短期記憶は比較的短い時間内に保存される情報のことを指し、例えば電話番号や一時的なリストの暗記などがこれに該当します。
これに対し、長期記憶は時間が経過しても保持される記憶で、学習した知識や人生経験などが含まれます。
「覚える」は、短期記憶や意識的に努力して記憶することに関連しやすいです。
例えば、試験のために公式や単語を覚える場合は、意図的に努力して短期間で記憶することが求められます。
一方で、「憶える」は長期記憶や無意識的に心に刻まれる記憶に関係が深く、特定の出来事や感情を伴う記憶に結びつきやすいです。
覚えると憶えるの使い分けに関する知恵袋
「覚える」は主に学習や暗記が必要な場面で使われ、短期間で知識を獲得することを目的とする場合に適しています。
たとえば、新しい言語を学ぶ際の単語の習得や、仕事のマニュアルの暗記などが該当します。
一方で、「憶える」は感情や印象を伴う記憶に関係しやすく、意識せずとも心に残る出来事を記憶する際に使われることが多いです。
例えば、大切な人との思い出や感動した映画のシーン、あるいは特定の香りが過去の記憶を呼び覚ますような状況では「憶える」が適しています。
このように、「覚える」と「憶える」は記憶の種類や性質に応じて使い分けることで、より的確な表現が可能となります。
類語とその使い分け

覚えるの類語
- 暗記する
- 学ぶ
- 習得する
憶えるの類語
- 思い出す
- 記憶する
- 留める
類語を使った例文
- 「過去の経験を思い出す(憶える)。」
- 「新しい単語を暗記する(覚える)。」
覚えると憶えるの正しい読み方
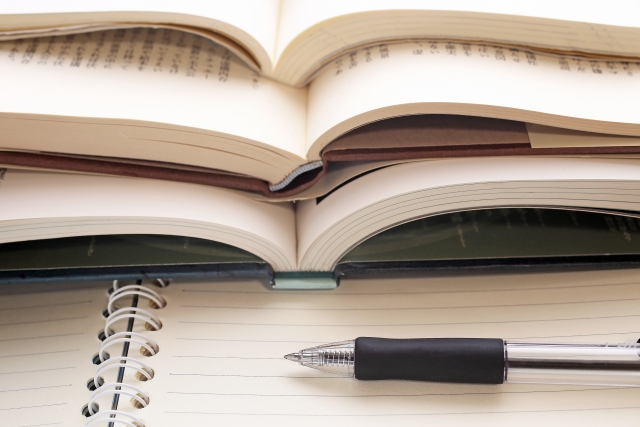
覚えるの正しい読み方と意味
「覚える(おぼえる)」は「知識や技術を身につける」という意味です。
これは、学習や経験を通じて新しい情報を取得し、それを長期的に保持することを指します。
例えば、語学の勉強では新しい単語や文法を覚えることが重要であり、試験や資格取得のためには専門知識を覚える必要があります。
また、運動技術や楽器の演奏技術など、反復練習を通じて習得するスキルにも「覚える」が使われます。
憶えるの正しい読み方と意味
「憶える(おぼえる)」は「記憶や感情を心に留める」という意味です。
これは、単なる情報の記憶ではなく、特定の出来事や体験を通じて得られる感覚や感情を心に刻むことを指します。
例えば、幼少期の思い出や、大切な人との会話、特別な出来事に対する印象などが「憶える」の対象となります。
また、懐かしい香りや音楽を聞いたときに過去の出来事が自然と思い出されることも、「憶える」に含まれます。
読み方の誤解を防ぐために
「覚える」と「憶える」を混同しないように、文脈に応じて正しく使い分けることが大切です。
「覚える」は主に学習や技能習得に関連し、「憶える」は経験や感情を伴う記憶に関係しています。
たとえば、新しい言語を学ぶ際には単語や文法を「覚える」ことが重要ですが、旅先での印象深い経験や感動した映画のワンシーンは「憶える」ことになります。
このように、それぞれの言葉が持つニュアンスを理解し、適切に使い分けることで、より正確で自然な表現が可能になります。
覚えると憶えるに関する用語集
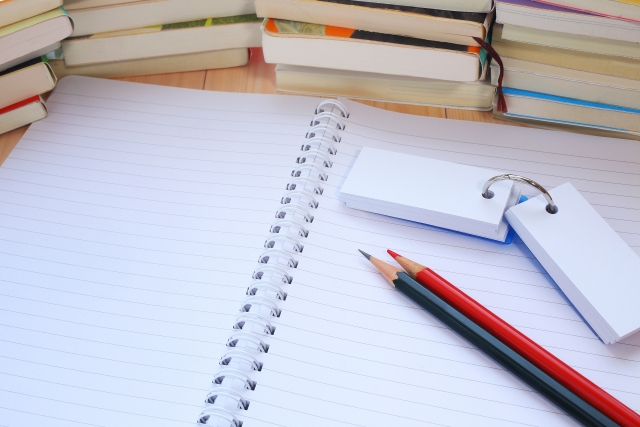
関連用語とその意味
- 暗記:短期間で情報を記憶すること。
- 記憶:情報を長期間保持すること。
- 追憶:過去を思い出すこと。
覚えると憶えるの重要性
言葉を正しく使うことで、より正確な表現ができるようになります。
特に、日本語においては微妙な意味の違いが文章のニュアンスや意図を左右するため、「覚える」と「憶える」を適切に使い分けることが重要です。
例えば、学習や暗記に関する話題では「覚える」を用い、感情や体験の記憶について述べる場合には「憶える」を選択することで、より自然な表現になります。
また、この違いを理解することで、文章を書く際や会話の中で的確な単語選びができ、読者や聞き手に意図を伝えやすくなります。
例えば、日常会話やビジネスシーンにおいても、情報を記憶する場合は「覚える」、過去の出来事を振り返る際には「憶える」を使うことで、言葉の意味が明確になり、コミュニケーションの精度が向上します。
関連する日本語の言葉
「記す」「認識する」「思い返す」「想起する」「留める」などがあります。
これらの言葉も、文脈に応じて適切に使い分けることが重要です。
文化的背景
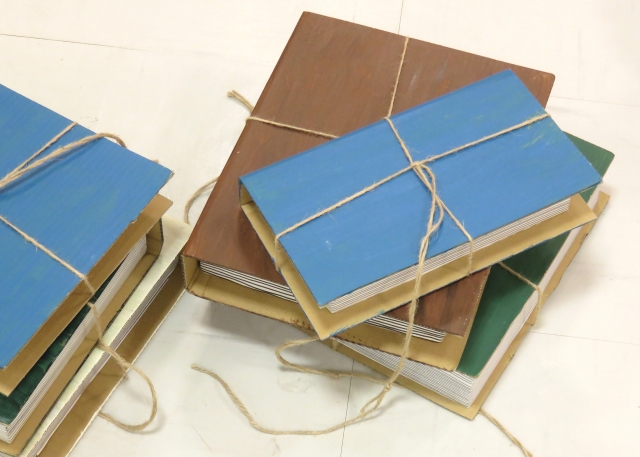
日本語における覚えると憶えるの歴史
古典日本語では「憶える」が多く使われていましたが、近代以降「覚える」が一般的になりました。
これは、時代とともに言葉の使われ方が変化し、より簡潔で汎用性の高い漢字が広く普及する傾向にあるためです。
特に、教育の現場や公式な文書では「覚える」が用いられることが増え、日常生活においても一般的な表現として定着しました。
しかしながら、「憶える」は完全に廃れたわけではなく、文学作品や詩歌などの表現においては、今でも感情や記憶の深さを強調するために使われることがあります。
特に、古典文学では「憶える」が頻繁に登場し、過去の思い出や感情のこもった回想を描写する際に重要な役割を果たしています。
また、日常会話でも感情を伴う記憶について話す際には「憶える」が適しているとされています。
言葉の文化的な違い
日本語では「覚える」と「憶える」を使い分けますが、英語では「remember」などに統一されることが多いです。
そのため、日本語話者が英語を学ぶ際には、このニュアンスの違いを理解することが重要です。
例えば、試験勉強や暗記の場面では“memorize”が適しており、過去の出来事や感情的な記憶について述べる場合には“recollect”や”remember”が適しています。
こうした文化的背景の違いを理解することで、言葉の持つ意味の奥深さをよりよく捉えることができるでしょう。
他の言語との対比
- 英語:「memorize」と「recollect」
- 中国語:「记住(覚える)」と「记忆(憶える)」
まとめ

「覚える」と「憶える」は同じ読み方を持ちながら、使い方や意味に違いがあります。
「覚える」は知識や技術の習得、暗記といった意識的な記憶に関連し、「憶える」は経験や感情、印象の記憶に使われることが多いです。
この違いを理解し、適切に使い分けることで、より正確で豊かな表現が可能になります。
また、言葉の文化的背景を理解することも重要です。
古典日本語では「憶える」が多用されていましたが、現代では「覚える」が一般的に使われるようになっています。
それでも文学作品や特定の場面では「憶える」が適していることがあるため、場面に応じた使い分けを意識するとよいでしょう。


