「こども」という言葉には、「子ども」と「子供」という2つの表記があり、どちらを使うべきか迷ったことはありませんか?
中には、「『子ども』と書くのが正しくて、『子供』は差別的だから避けるべき」という意見を耳にしたことがあるかもしれません。
では実際に、「子供」という表記にはどのような由来があり、なぜ「使わないほうがいい」と言われることがあるのでしょうか?
この記事では、「子供」という漢字の意味や背景、そして近年の表記の流れや使い方の違いについて、わかりやすく解説していきます。
「子ども」と「子供」、正しい表記はどっち?
「子ども」と「子供」は、どちらも誤りではなく、正しい表記として認められています。
一般的には「子ども」という表記をよく見かけますが、これはルールで定められているものではありません。
使用ルールが統一されているわけではなく、報道機関や行政機関など、組織によって使い分けられています。
以下に、主な団体の表記ルールをご紹介します。
NHKの表記ルール
NHKでは原則として「子ども」と表記しています。
ただし、文脈によっては「子供」と書かれる場合もあり、柔軟に使い分けられています。
厚生労働省・こども家庭庁の場合
厚生労働省やこども家庭庁では、基本的に「こども」とひらがな表記を採用しています。
ただし、固有名詞や文脈によって必要がある場合には、「子ども」または「子供」の漢字表記が使われることもあります。
新聞社の方針
新聞各社では、「子ども」「子供」「こども」いずれの表記も見られます。
ただし、1つの記事の中では表記を統一するのが一般的なルールです。
「こどもの日」がひらがなな理由
5月5日の「こどもの日」は、1948年に制定された国民の祝日です。
この名称がひらがなで書かれているのは、子どもたちが読みやすく、親しみを持ちやすいようにという配慮からです。
「子供」という漢字の成り立ちと歴史的背景
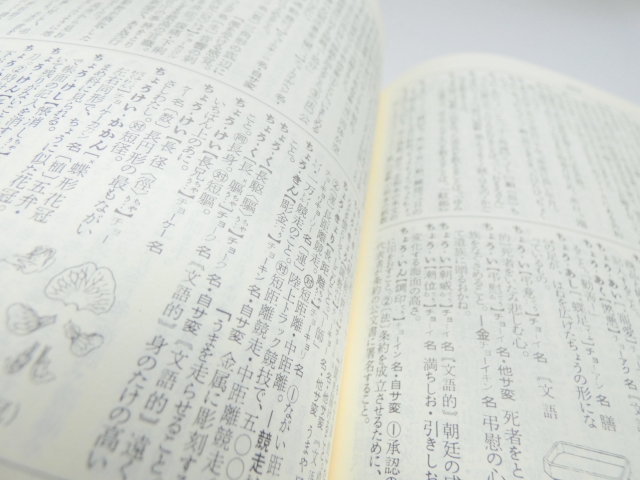
「こども」の「ども」は、もともと複数や従属を意味する接尾語とされています。
そのため、「子ども」という言葉には「複数の子どもたち」や「目下の存在」といったニュアンスが含まれていたと考えられています。
この語が日本語としていつ頃から使われ始めたのかは明確ではありませんが、日本最古の和歌集『万葉集』(759年成立)にはすでに「子ども」という表現が見られます。
なかでも山上憶良(やまのうえ の おくら)の歌には、「子ども」にまつわる情緒豊かな詩が複数残されています。ここでは代表的な二首をご紹介します。
「いざ子ども 早く大和へ」
いざ子ども 早く大和へ 大友の 御津の浜松 待ち恋ひぬらむ
この歌は、「さあ皆、早く大和の国へ戻ろう。大友の御津の浜松が、私たちの帰りを待ちわびているだろう」という旅の仲間たちへの呼びかけの詩です。
ここでの「子ども」は、同行する部下や仲間を指しているとも言われますが、現代で言う「子どもたち」のような意味合いで捉える解釈も存在します。
「瓜を食べれば 子どもが恋しい」
瓜食めば 子ども思ほゆ 栗食めば まして偲はゆ
いづくより 来りしものそ 目交に もとなかかりて 安眠しなさぬ
この和歌は、遠く離れて暮らす我が子への想いを詠んだ父親の情感あふれる作品です。
何気ない食事の中で子どもの面影が浮かび、涙ぐみながら眠れない夜を過ごす――そんな切ない情景が描かれています。
この場合の「子ども」は、まさに現代の「わが子」という意味で広く解釈されています。
「子供」表記への変遷と統一の流れ
江戸時代に入ると、「子供」という漢字表記が次第に広まり始めます。
ただし当時は、「子ども」「子共」「子等」「こども」など、さまざまな表記が混在しており、書き方に統一性はありませんでした。
この混乱が次第に収束していったのは、明治時代以降のことです。
公文書や出版物の増加に伴い、表記の標準化が求められるようになり、「子供」という漢字表記が広く用いられるようになっていきました。
なぜ「子供」という表記が避けられることがあるのか?
かつては「子供」という漢字表記が一般的に使われていましたが、2000年代に入ってからは、「供」という字に対する違和感を理由に、使用を避ける動きが広まりました。
具体的には、以下のような理由が挙げられます。
- 「供」という字が「お供」や「付き従う者」を意味し、子どもを大人の従属的な存在として見る印象を与える
- 「供養」や「供え物」といった言葉を連想させるため、子どもに使う漢字としてはふさわしくないという意見
こうした声を受けて、「子ども」とひらがなを交えた表記を採用する報道機関や教育機関が増えていきました。
ただし、平成25年(2013年)に文部科学省は、「子供」は常用漢字に含まれていることから、公文書では「子供」を使用する方針を明示しています。
その影響もあり、近年では再び「子供」と表記するメディアも増えてきています。
実際のところ、「子供」という表記に差別的な意味合いがあるわけではなく、「当て字」に過ぎないというのが専門家の見解です。
つまり、「子ども」と「子供」のどちらを使っても誤りではなく、その使い分けは個人や組織の判断に委ねられているのが現状です。
まとめ
「子ども」と「子供」はどちらも正しい表記であり、明確な使い分けのルールはありません。
2000年代以降、「供」という漢字に対する印象の変化から「子ども」と表記するケースが増えましたが、「子供」に差別的な意味があるというのは誤解とされています。
さらに、文部科学省は公文書において「子供」を用いる方針を示しており、今後は「子供」という表記が再び増えていく可能性もあります。
場面や媒体に応じて、それぞれの表記をバランスよく使い分けていけると良いですね。


